生成AI

ここ数年、IT業界やニュース、SNSを見ていると、必ずといっていいほど「生成AI」という言葉を耳にするようになった。
ChatGPTをはじめ、GeminiやClaude、画像生成AIのStable DiffusionやMidjourneyなど、多種多様なツールが登場し、
「AIで文章が書ける」「AIでイラストが描ける」と話題になっていた。
しかし、正直に言うと、私はずっと傍観者だった。Twitterで流れてくるAIのエロ絵にいいねするくらいで、5ch住人たちの「こんなスクリプトでこんな絵ができた!」という話を見聞きしながらも、「へえ~メモメモ」と思う程度。SEという仕事をしているのに、世間のITトレンドからすっかり取り残されていた。
そんな私がついにAIに手を出すことになったのは、仕事でCopilotを使い始めたことがきっかけだった。実施したい内容を入力するだけで、batファイルやbatファイルの修正案をAIが提案してくれるあれだ。最初は「本当に使えるのか?」と半信半疑だったが、いざ試してみると、思っていた以上に精度が高い。簡単な処理ならほぼ一発で出力されるし、曖昧な指示でも意図をくみ取ってくれる。
そして、気づいたら家でもChatGPTを触り始めていた。
AIに任せられることの広さ
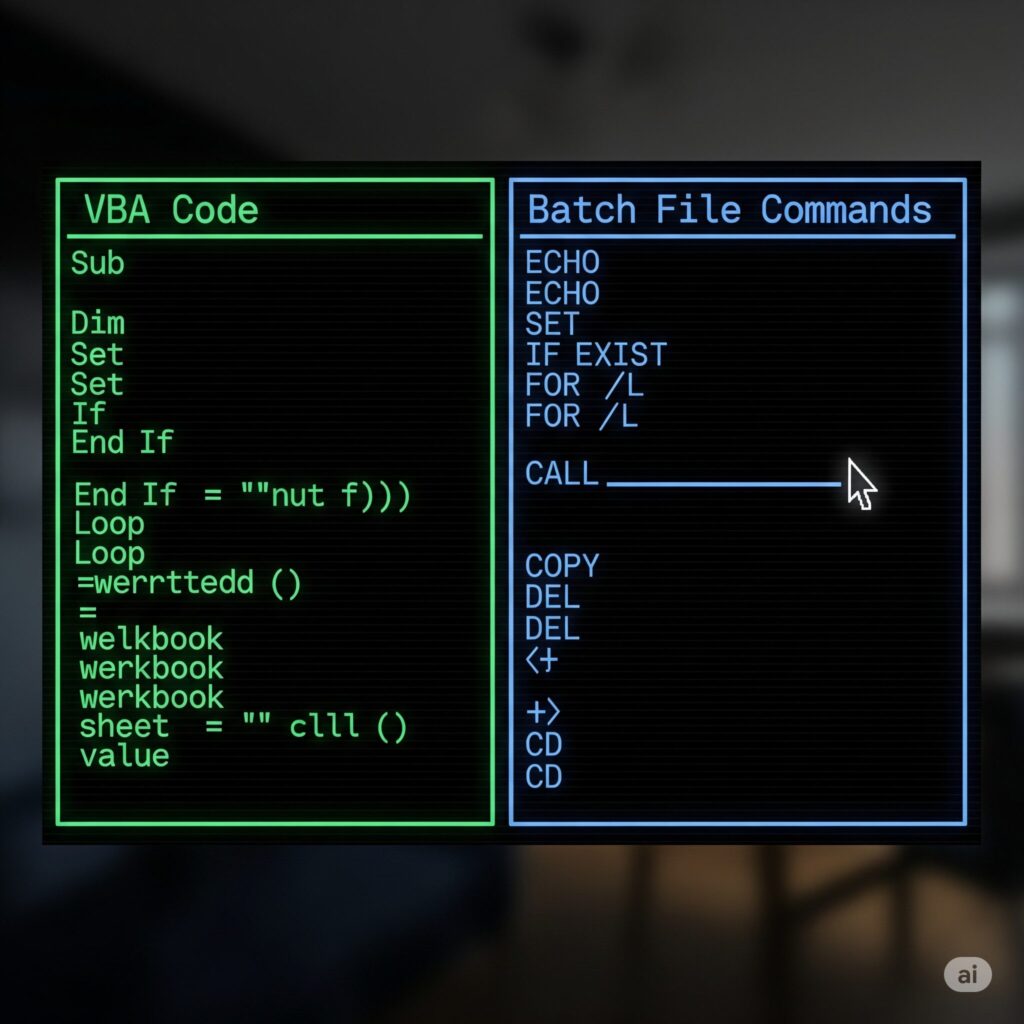
初めてChatGPTに頼んだのは、Excelで使う簡単なマクロだった。VBAの細かい構文は忘れてしまっていても、「特定のシートをコピーして日付をファイル名に入れて保存するマクロを作って」とお願いするだけで、数秒後にはコードが出てくる。
さらに試しに、「指定フォルダ内のファイル一覧をテキストで出力するバッチファイルを作って」と聞いてみたら、こちらも即答。コマンドプロンプトの書き方を思い出す必要すらなかった。
面白いのは、少し複雑なものでもAIに“たたき”を作らせ、それを動かしてみてエラーが出たら、そのエラー内容をそのまま投げ返すと、「ではこう修正しましょう」と代替案を返してくれるところだ。内容を100%理解していなくても、何度か往復すれば完成形に近づいていく。まるでリモートにいる有能な後輩に相談しているような感覚だ。
初めて感動した瞬間

一番「これはすごい」と感じたのは、会社での人間関係に関する相談をChatGPTにしたときだ。
私の職場には、いわゆるブリリアントジャークが何人かいる。頭はキレるし知識も豊富だが、会話の中で余計な悪口や愚痴を差し込んでくるタイプだ。彼らとの会話からは確かに有用な情報も得られるのだが、それは全体の2〜3割程度。残りは精神的に削られるような内容で、正直、打ち合わせが終わるたびに疲弊していた。
そこで、半ば冗談のつもりでChatGPTに似たような相談をしてみた。すると、返ってきた答えの7〜8割は的確で、残りの2〜3割はやや見当外れではあったものの、それは私の質問が省略しすぎていたり、行間を読ませるような聞き方をしてしまったせいだとすぐに気づいた。
何より驚いたのは、その言い回しや説明が非常に丁寧で、こちらを気遣うニュアンスすら感じられたことだ。淡々と事実を述べるのではなく、「あなたの状況はこうで、こういう対処法がありますよ」と、まるで落ち込んでいる同僚を励ますような文章で返してくれる。社内のブリリアントジャークたちよりも、ずっと優しく、穏やかで、しかも有用な助言をしてくれるのだ。
このやり取りは、私にとって「AIって人間と変わらないんじゃないか?」と思わせるきっかけになった。もちろんまだ発展途上ではあるが、少なくとも精神的な負担の少ないコミュニケーションパートナーとしては、すでに十分役立つと感じた。
この記事もAIが作成している?

実は今書いているこの記事も、箇条書きに書きたいことを羅列した内容に沿って文章構成や見出しをAIに作ってもらっている。
とはいえ、そのままでは“ブログ”とは呼べない。
AIが作る文章は論理的で読みやすいが、どこか無味無臭になりがちだ。個人の体験談や感情、ちょっとした失敗談など、いわゆる“人間らしいムラ”がない。読者の立場からすると、「これAIじゃない?」と気づく段階だと思うし、私自身も書いていてそう感じる。
結局、AIは“骨組み”や“下書き”を作るのに向いていて、肉付けや仕上げは人間がやるべきだと実感した。
AIで株取引?
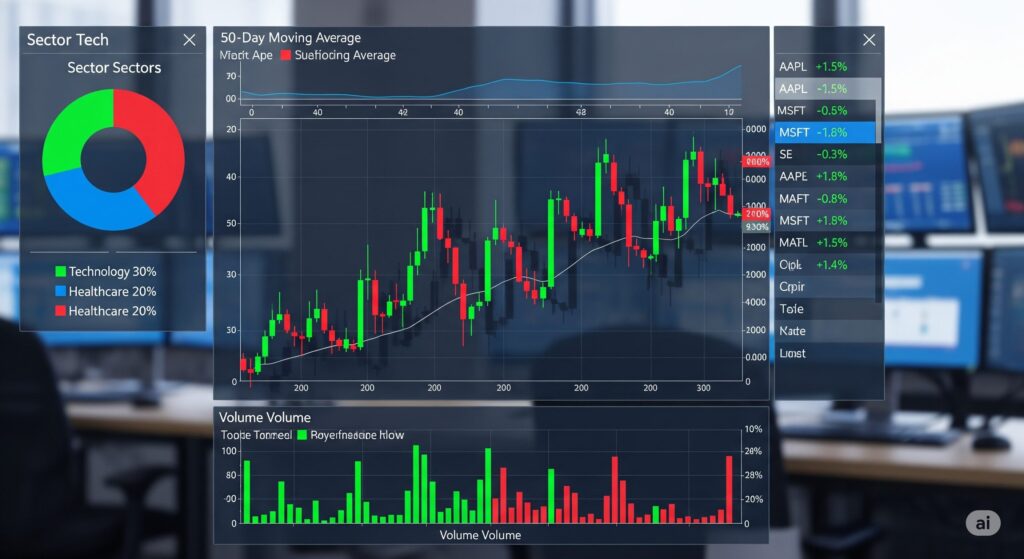
AIの可能性を考えていくと、「じゃあ株取引にも使えそうじゃないか」という妄想も湧いてくる。過去データやリアルタイムの市場情報を分析し、売買タイミングを自動で判断してくれる……そんな仕組みがもし個人レベルで使えたら、夢が広がる。
ただ、現実的にはまだ難しいだろうと思う。過去に流行したバイナリーオプションだとか自動売買で絶対儲かるみたいな話を思い出す。どれもこれも詐欺みたいな話だった。もしAIによる自動株取引が本格的に普及したら、皆が一斉にAIを導入し、売買が過熱して市場が混乱する未来も容易に想像できる。
どこぞのAI同士では市場競争せずに談合を始めたとか。
SEとしての反省と展望

今回、CopilotやChatGPTを実際に使ってみて、「もっと早く試せばよかった」と痛感した。最新の技術を触らないまま情報だけ追っていても、実感は得られない。手を動かして初めて分かることがたくさんある。
SEという職業は、知識だけでなく実践力が求められる。AIがどこまでできるのか、逆にどこからが人間の領域なのかを、自分の手で試しながら線引きしていくことが大切だと感じている。
今後は、日常的な小さなスクリプト作成から、ブログの下書き、さらには業務の効率化まで、積極的にAIを取り入れていきたい。そして、その過程や失敗も含めて、こうしてブログに残していけたらと思う。
まとめ
AIは「万能の魔法の杖」ではないが、正しく使えば圧倒的な作業効率化ツールになる。
世間の流行から少し遅れてしまったけれど、これからはSEとして、そして一人の好奇心旺盛な人間として、AIと上手に付き合っていきたい。